|
2025/5/18
|
|
ピアノ、という楽器について |
|
|
”ピアノ”と言えば 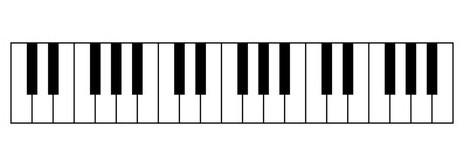 でも、この”鍵盤”を使う楽器は、”ピアノ”だけではないのです。 あまり身近ではありませんが、教会のパイプオルガン、チェンバロ、クラヴサン等 ピアノのご先祖ともいえる楽器(どれも現役で活躍している楽器ですけどね)、 幼稚園や小学校で使う鍵盤ハーモニカ、 メーカーによって名前は様々ですが、電子オルガン(エレクトーンとかドリマトーンとか)、 そしてシンセサイザー、等もこの鍵盤を使って演奏します。 どれも、10本の手の指を駆使して演奏する楽器です。パイプオルガンや電子オルガンは、なんと足も使う豪華版です。 音の出る仕組みもそれぞれです。 パイプオルガンや鍵盤ハーモニカは、空気を送り込むことによって”リード”という部品が振動して音を出します。 チェンバロやクラヴサンは、張ってある”弦”を爪のようなもので”引っ掻く”ことによって音を出します。 電子オルガンやシンセサイザーは、電気回路による発信音を用いた楽器で、色々な波形の音を組み合わせたり、サンプリングした音源を使ったりして、本物の楽器に近い音や、幻想的・宇宙的な音を出せる機械、楽器です。鍵盤はその電子回路のon、off、を司るスイッチの役目をします。 では、”ピアノ”は、どんな仕組みで音が出るのでしょうか? (ここでは電気を使わない、アコースティックのピアノを題材とします。) 現代のピアノは、様々な太さや長さのワイヤー(弦)を、フェルトで覆われたハンマーで叩くことによって音を出す楽器です。 叩かれた弦の振動に、他の多くの弦が共鳴したり、周りの流線形の黒い板や色々な部品がその響きを増幅したりすることで、”ピアノの音色”を作ります。 ちょっと気持ちが入っちゃって文字色が赤くなってしまいましたが、この、共鳴・響きの増幅、が、空間に広がる心地良い音の世界を作るのです。 どんなにシンプルな単音だけの歌でも、どんなに複雑で難解なテクニックを駆使した曲でも、この、共鳴と響きの増幅を味方につけなければ、しょぼい下手くそな演奏に聴こえてしまいます。 なので私たちピアノ弾きは、どうやったら素敵な響きを出せるだろう、いろいろな感情や意図を音に乗せることができるだろうか、と日々苦闘するわけです。 レッスンしに来て下さる小さなお子さんにも、 『ただ押せば音の出る鍵盤、でも指や腕や身体の使い方によって、とっても素敵な音を響かせることができる装置』ということをお伝えしたいと、日々思っています。 そして、これまで話題に出さなかった『電子ピアノ』というジャンルがあります。 これは、鍵盤の弾き具合をや音質をピアノに近づけた、シンセサイザーの一分野です。 年々進化していて、弾き具合が実際のアコースティックピアノにかなり近くなっているものも多く、驚かされます。 スイッチひとつで色々なピアノの音色に変えられたり、他の楽器(オルガンやチェンバロ、ビブラフォンやコーラス等)の音も出せますし、ピアノの名曲のデモ演奏も内蔵されていたりします。すばらしい。 私は毎月一回、近くの子育て支援センターにて音楽ボランティアをさせて貰っていますが、その日のキャッチフレーズは「ピアノのちえちゃん♪」です。てへ。 「ピアノのちえちゃん」ではありますが、実際そこで演奏するのは電子ピアノです。 なら「電子ピアノのちえちゃん」にすればよかろうに、と思われるかもしれませんが、生憎”電子ピアノ”としてのスペックは使いこなせておらず、あくまで”ピアノ”の代替品としてしか使っていないため「ピアノの」となるわけです。 支援センターのある建物には、別コーナーにアップライトのピアノが設置されており、いわゆるストリートピアノの位置づけで使われていますが、それを月に一度の15分のために子育て支援センターの場所にまで運ぶには、いかんせん重すぎます。 かといって、ずっと支援センターにどっかりとアプライトピアノを鎮座させても邪魔なだけですよね。 こんな場合に『電子ピアノ』はまことに重宝なんですね。重いけど、運べないほどではない。使いたい時にすみっこの部屋から運び出して活躍させられる。音量も調節できる。ご家庭では、ヘッドフォンも使えるから夜中も練習できる。本当に便利です。 私も、手持ちの電子ピアノに助けられることが多いです。 生徒さんも、ご家庭では電子ピアノで練習されている方がほとんどですね。 電子ピアノというものがこの世に無かったら、ピアノを始めよう!と思う方がだいぶ少なくなっていたのではないかと思います。 ただ、やはり電子ピアノでは共鳴や響きの広がりをどう作るかを追求するのは難しいですね。 鍵盤上で指をどう動かすか、という練習を家の電子ピアノでしてきて貰って、レッスンではアコースティックの響きを感じつつ、素敵な響きを作る工夫を体験して貰いたいと思っています。 |
|
| |


